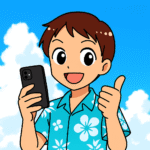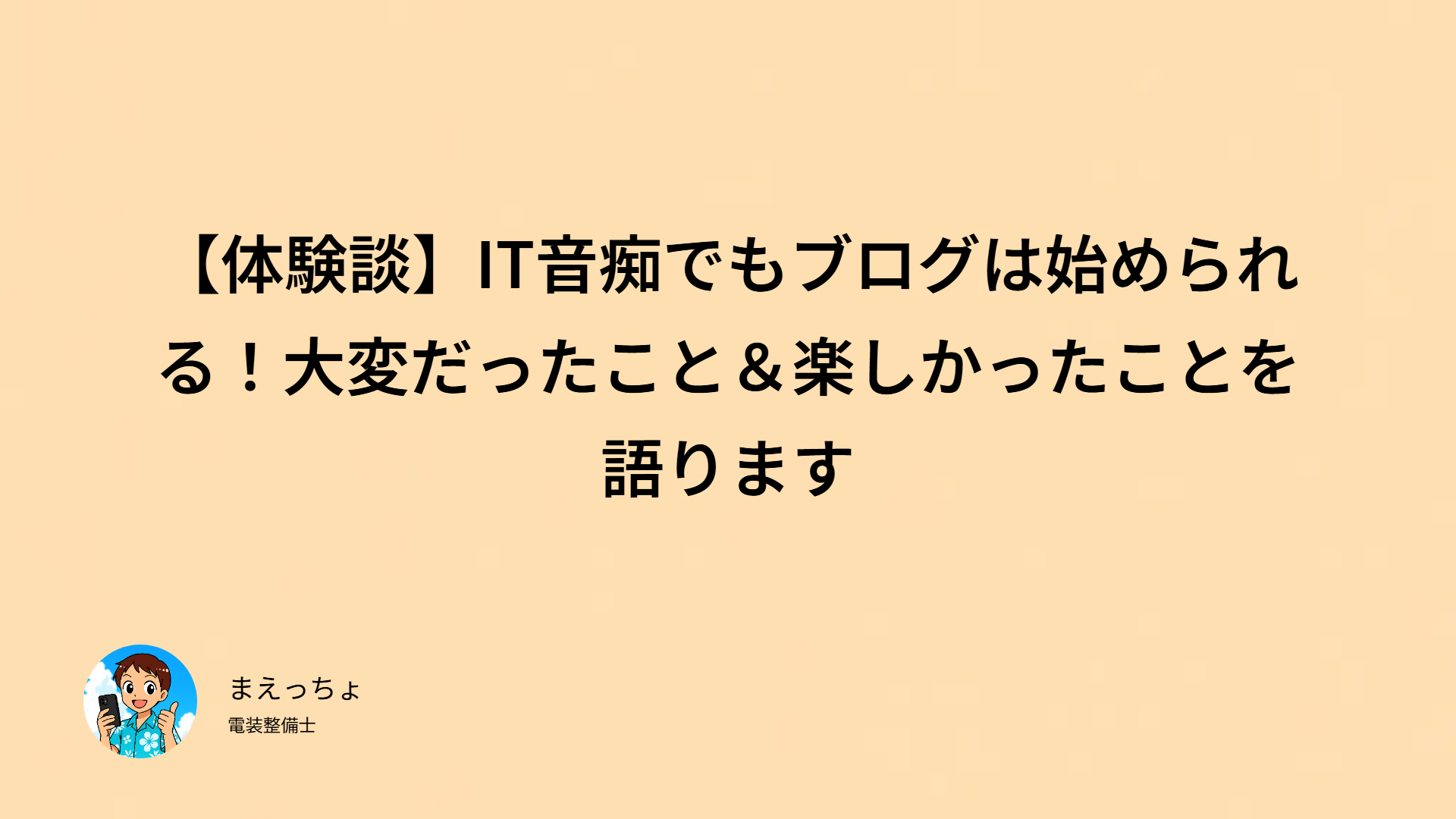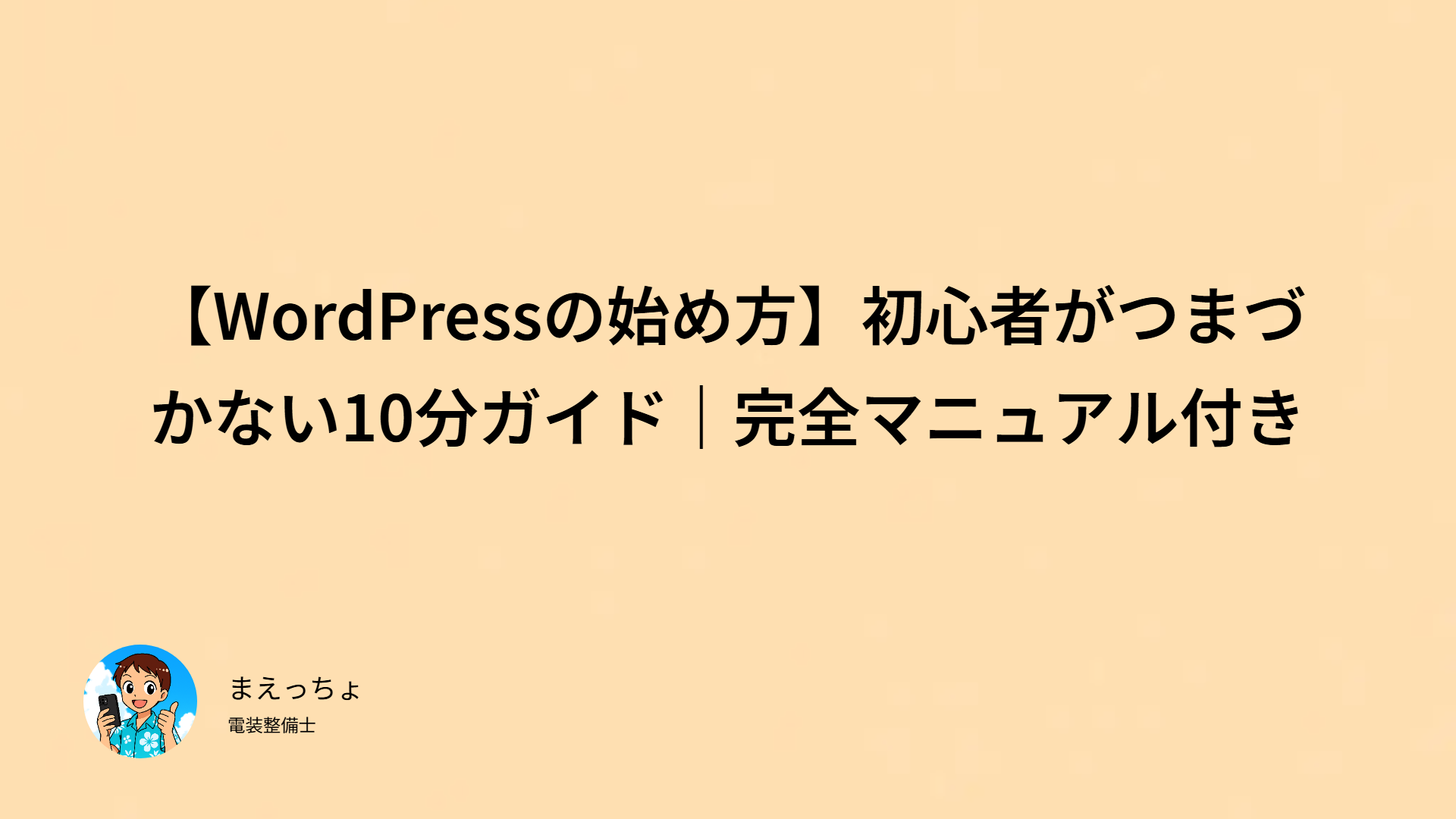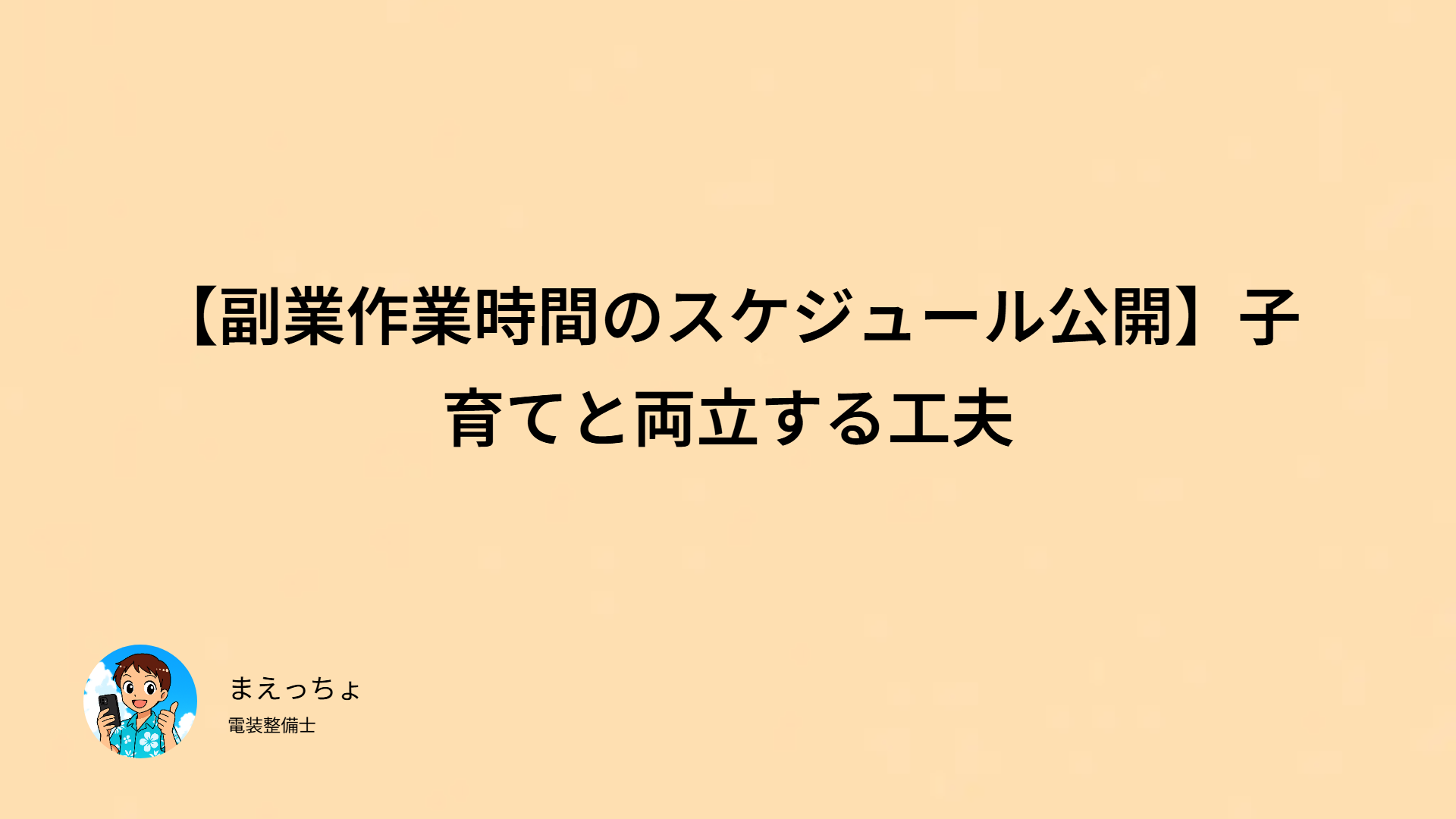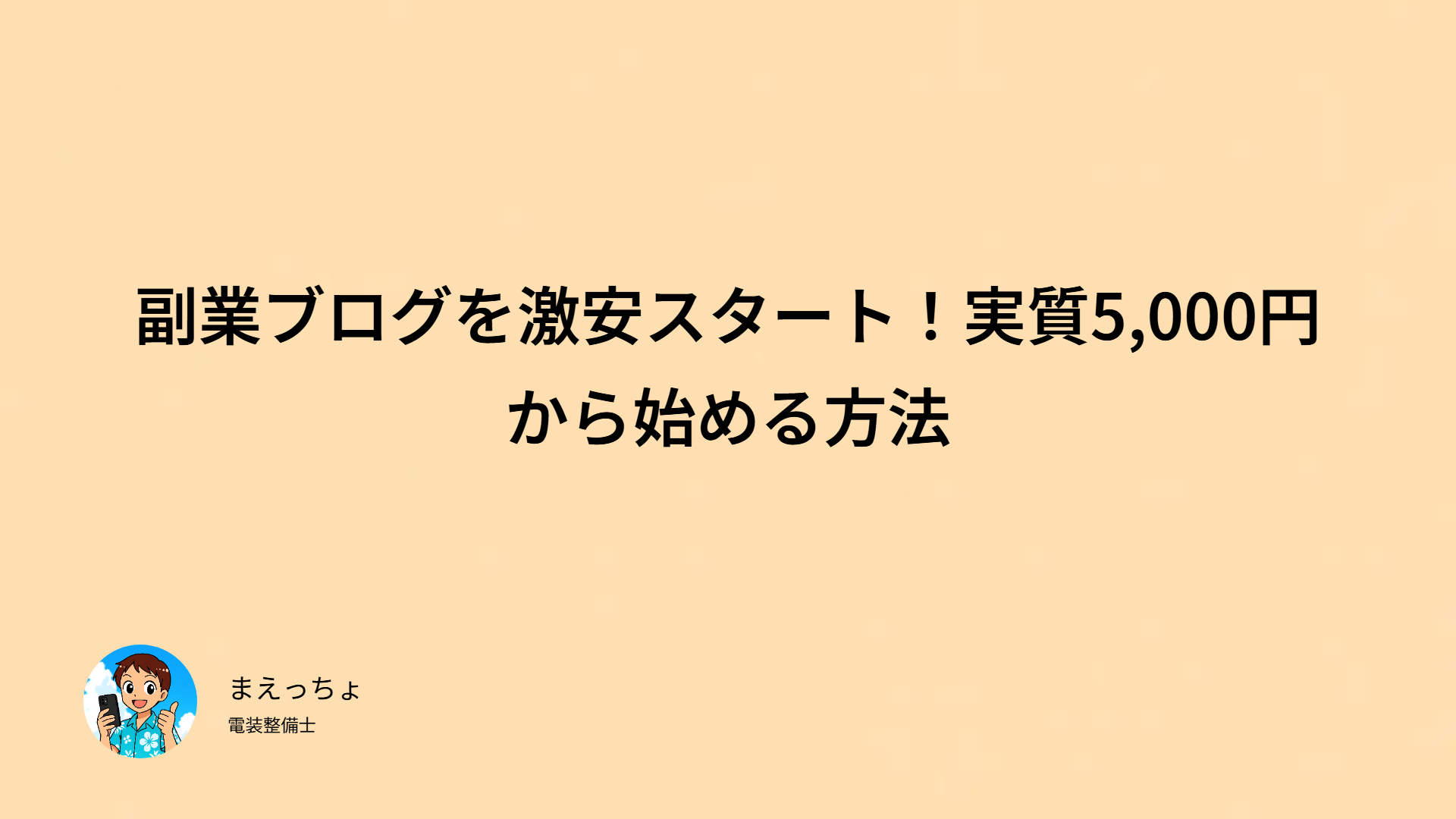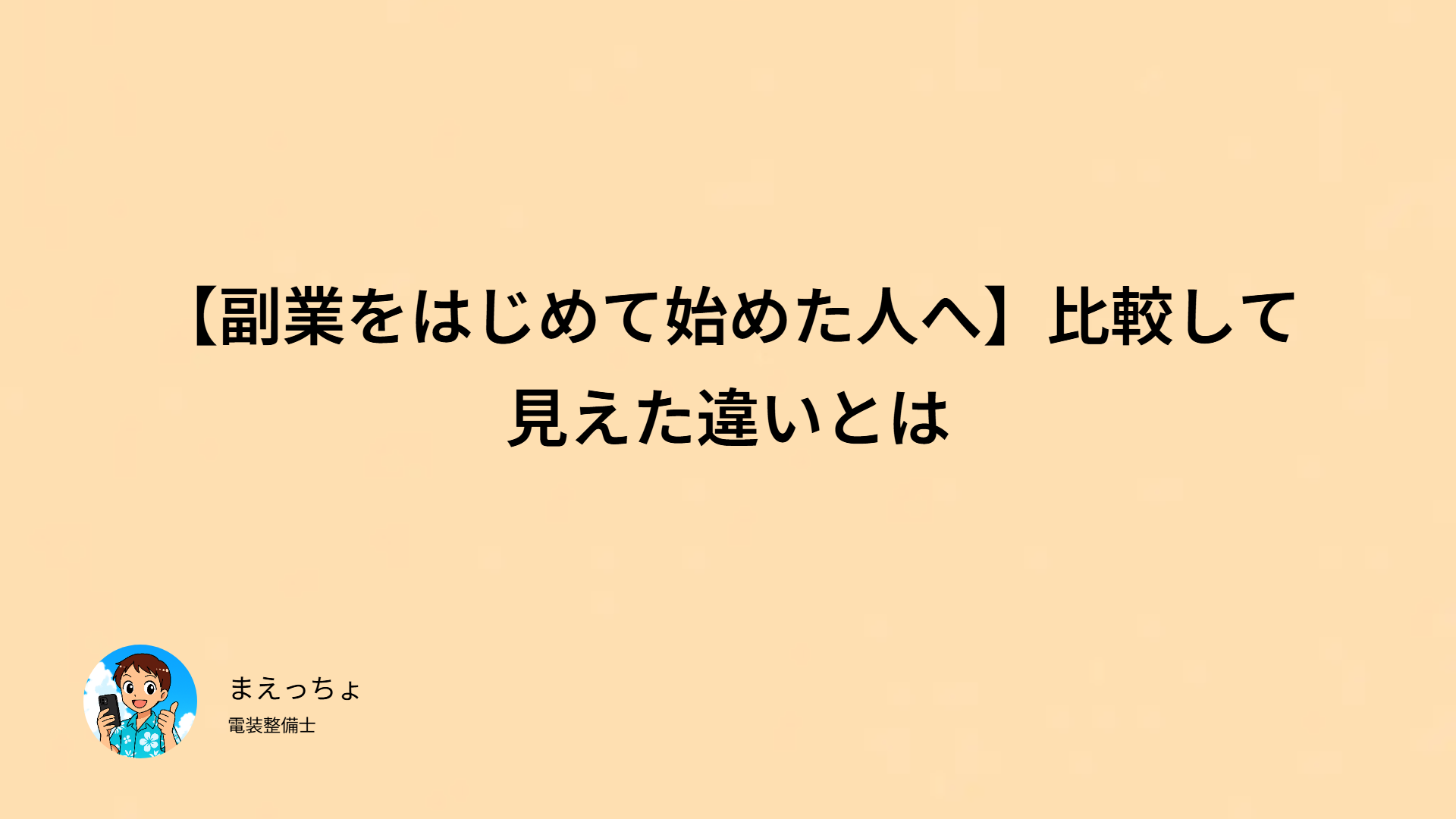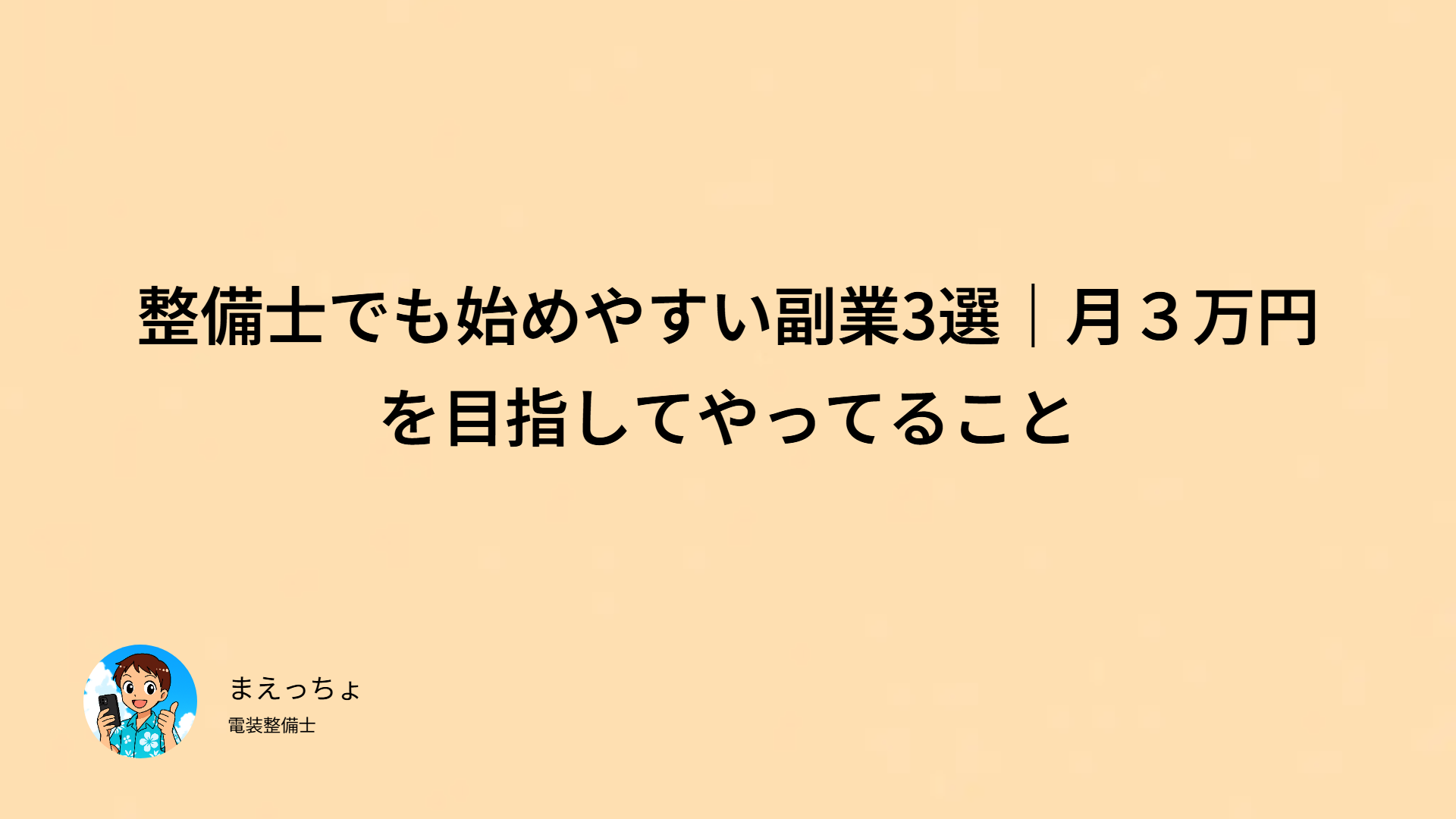【副業ブログのSNS活用術】Xで実践した成功と失敗の体験談
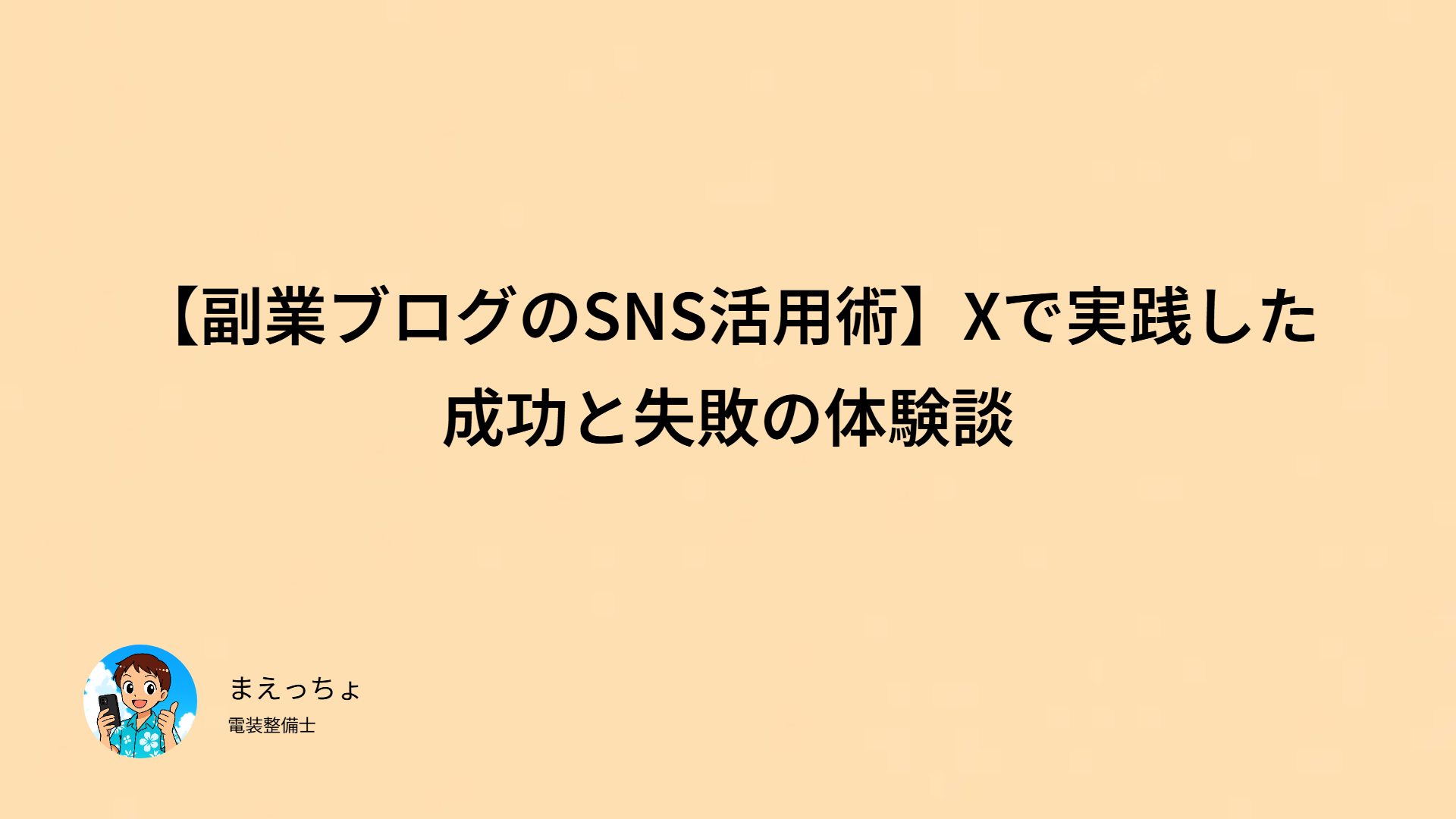
ブログを始めたばかりの頃、検索からの流入はゼロ。
書いても誰にも届かない虚しさを感じていました。

そこで挑戦したのが、Xを使った副業ブログのSNS活用。
日常や悩みを発信するうちに「自分も同じだよ」と共感してくれる仲間が増え、書き続ける力につながったんです。
この記事では、私が実際に試したSNS活用法と、そこから得られた気づきをお伝えします。
なぜSNSを副業ブログに取り入れたのか
検索流入ゼロの現実
ブログを立ち上げたばかりの頃、サーチコンソールを開いても「0」の数字が並ぶだけでした。
どれだけ記事を書いても、Google検索からの流入はほとんど期待できません。
書いた記事が読まれない状況は、正直かなりつらい。
「このまま続けて意味があるのかな」と迷う瞬間もありました。
誰かに読んでもらいたい気持ち
それでもブログを続けたいと思ったのは、「誰かの役に立てたら」という思いがあったからです。
家計管理の工夫や副業の取り組み、投資の記録。
自分が積み重ねてきたことを、同じように悩んでいる誰かに届けたい。
そう考えたとき、検索だけに頼らず「自分から発信してつながる手段」が必要だと感じました。
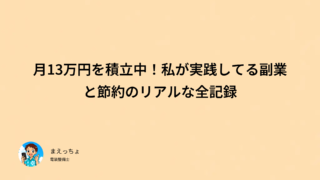
Xを選んだ理由と最初の投稿
そこで選んだのがSNS、特にX(旧Twitter)でした。
理由はシンプルで、拡散力があり、気軽に始められるから。
最初の投稿はたわいもないものでしたが、「ブログを書いています」「副業を始めました」と自己紹介を兼ねて発信しました。
すると、同じように副業や投資に取り組んでいる人からフォローや反応がもらえたんです。
その小さなつながりが、私にとって大きな一歩になりました。
パパの日常と副業の発信スタイル
発信内容は特別なものではありません。
子育て中のパパとしての日常や、ブログを運営しながら感じる悩み。
そして副業や投資の小さな成果をときどきシェアする。
それだけでも「同じ境遇です」「共感します」と声をかけてもらえることがありました。
検索流入がゼロでも、Xを通じて自分の言葉が誰かに届く。
その実感が、ブログを続ける強いモチベーションになっていったのです。
私が実践したSNS活用法
毎日1〜2回の投稿ルール
Xを始めてから意識したのは「継続して発信すること」でした。
ただ、無理をすると続かなくなるので、毎日1〜2回の投稿を目安にしました。
朝や夜など、生活の中で無理なく投稿できるタイミングを決めることで、習慣として続けやすくなったんです。
このリズムができてから、SNSをストレスではなく「日常の延長」として取り入れられるようになりました。
記事リンクは控えめにした理由
最初の頃は「ブログに来てほしい」と思って、記事リンクを何度も投稿したこともありました。
でもそれではフォロワーに飽きられてしまうし、逆に反応も減ってしまうんです。
そこで私は、記事リンクをシェアするのは本当にたまに。
むしろ「記事を書いた背景」や「記事に書ききれなかった日常のエピソード」を中心に発信しました。
結果として「人となり」に共感してくれる人が増え、自然にブログも読んでもらえる流れが生まれたんです。
日常や気づきを中心に発信
私の投稿の多くは、パパとしての子育てや、ブログを書いていて感じた小さな気づきです。
たとえば「節約記事を書いていると、昔は家計管理がザルだったことを思い出す」など。
完璧じゃない自分の経験を正直に発信することで、同じように悩んでいる人から共感をもらえることがありました。
SNSは「有益な情報を完璧に出す場所」ではなく、「共感や気づきをシェアする場所」だと感じています。
活用していたハッシュタグ
投稿を見てもらうために工夫したのがハッシュタグです。
よく使っていたのは #副業 #ブログ初心者と繋がりたい #投資家さんと繋がりたい の3つ。
これらは同じように副業やブログ運営に取り組んでいる人に届きやすく、フォローや交流につながりました。
ただ、ハッシュタグに頼りすぎるのではなく、投稿内容そのものが「共感されること」を意識することが大切だと思っています。
SNSを活用して得られたメリット
共感してくれる仲間との出会い
ブログを始めたばかりの頃は、孤独との戦いでした。
でもXで発信を続ける中で「同じように副業でブログを書いている」という仲間ができ、気軽に声をかけ合えるようになりました。
それは数字以上に心強い支えで、継続する力につながったんです。
アクセスがゼロでも続けられた理由
Google検索からの流入はゼロ。
それでも記事を公開するたびにSNSで紹介すると、必ず誰かがブログに訪れてくれる。
「誰かに読んでもらえた」という実感は、アクセス数が少なくても大きなモチベーションになりました。
「0」と「1」の差は、続ける気持ちに想像以上の影響を与えます。
アナリティクスで見えた小さな成果
ある日アナリティクスを確認すると、アクティブユーザー数はわずかでも、平均の閲覧時間が10分以上というデータが出ていました。
短い滞在時間ですぐ離脱されると思っていたので、この数字は驚きでした。
自分の文章を丁寧に読んでくれている人がいる。その事実が、私にとって何よりのご褒美になったんです。
ブログ仲間ができた安心感
SNSを通じて知り合った人の中には、同じように悩みを共有できるブログ仲間もいました。
コメントやDMで「お互い頑張ろう」と声を掛け合えることは、孤独な作業が多い副業ブログ生活にとって大きな救いでした。
数字の成果だけでなく、人とのつながりもまた、SNSを活用する大きなメリットだと感じています。
SNSでの失敗と学び
応援していた会社の発信に共感して
私には長期で応援している会社があります。
その会社の社長や専務がXでよく発信していることもあり、株主として共感する部分をときどき投稿していました。
あるとき「この会社は◯◯が良いよね」と感じたことをつぶやいたら、ありがたいことに多くのいいねやリツイートをいただけたんです。
同じ会社を応援する仲間がいることに、純粋に嬉しさを感じました。
思わぬ噛みつき
ところが、その投稿に噛みついてくる人が現れました。
しかも驚いたのは、その人も同じ会社の株を持っている株主だったことです。
自分ではポジティブな思いを共有したつもりが、まさか同じ株主から否定的に受け取られるとは思っていませんでした。
予想外の反応に、正直ショックを受けました。
言い返してしまった後悔
当時の私は感情的になり、相手に言い返してしまいました。
でも後から振り返ると、そのやり取りに時間も気力も奪われ、記事を書く手すら止まってしまったんです。
SNSは、文字だけが見える世界なので、ちょっとした言葉のズレが大きな対立に見えてしまうこともあります。
わざわざ応酬する必要はなかった、と深く反省しました。
励ましと学び
幸いにも、その後は多くの人から「気にするな」「応援してるよ」と励ましをもらいました。
その経験から学んだのは「全員と分かり合う必要はない」ということです。
今は、自分に合わないと思った人とは無理に交流しないようにしています。
その方がSNSとの距離感を心地よく保てるし、本業やブログに時間を残すことができる。
SNSは“つながりを増やす場”であると同時に、“距離をとる選択ができる場”でもあると実感しました。
副業ブログとSNSを続けて気づいたこと
SNSは検索の代わりになる
ブログを立ち上げたばかりの頃、Google検索からの流入はほぼゼロ。
でもXで発信すれば、誰かが必ず記事を読みに来てくれる。
これはまるで「小さな検索エンジン」のようなもので、SNSがブログの入り口になっていると実感しました。
人とのつながりが継続の力になる
SNSには否定的な声もありますが、それ以上に支えてくれる仲間の存在が大きいです。
同じように副業や投資に取り組んでいる人たちと交流することで、「自分だけじゃない」という安心感が得られました。
孤独になりがちな副業ブログにおいて、このつながりが継続のモチベーションになっています。
数字以上の価値を感じられる
アナリティクスを見てもアクセスはまだ少ない。
それでも「平均閲覧時間が10分以上」という数字を見たとき、自分の文章を丁寧に読んでくれる人がいるとわかりました。
フォロワー数やPVだけでは測れない価値がある。それがSNSとブログを続けて得られた大きな気づきです。
距離感を保つことが継続の秘訣
SNSは便利ですが、すべての人と関わろうとすると消耗します。
私の場合、自分に合わない人とは無理に交流せず、心地よい距離感で使うようにしました。
その結果、ブログ執筆に集中する時間が増え、SNSも前向きに活用できるようになったのです。
まとめ|SNS活用は副業ブログの大きな支え
SNSがあったから続けられた
ブログを始めた当初、検索からの流入はゼロに近くて、不安や孤独を感じることもありました。
それでもXで発信を続けたおかげで、最初の読者が生まれ、仲間ともつながることができました。
「誰かに読んでもらえる」という事実が、ブログを続ける大きな支えになっています。
成功も失敗もすべてが経験になる
SNSではいいねやリツイートに励まされることもあれば、意見がぶつかって消耗することもあります。
それでも一つひとつの経験が、自分にとっての財産になりました。
私にとってSNSは、単なる拡散ツールではなく「学びの場」でもあると感じています。
これからも自然体で続けたい
副業はマラソンのように長い道のりです。
だからこそ、SNSも背伸びせず、自然体で続けるのが一番。
応援してくれる人に感謝しつつ、自分のペースで発信を続けていくつもりです。
今回の記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
普段はXでも「副業ブログの気づき」や「家計のリアル」を発信しています。
このページの一番下にあるプロフィール欄から、Xアカウントにも簡単にアクセスできるので、よかったらチェックしてみてください。