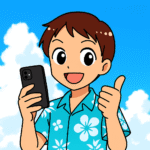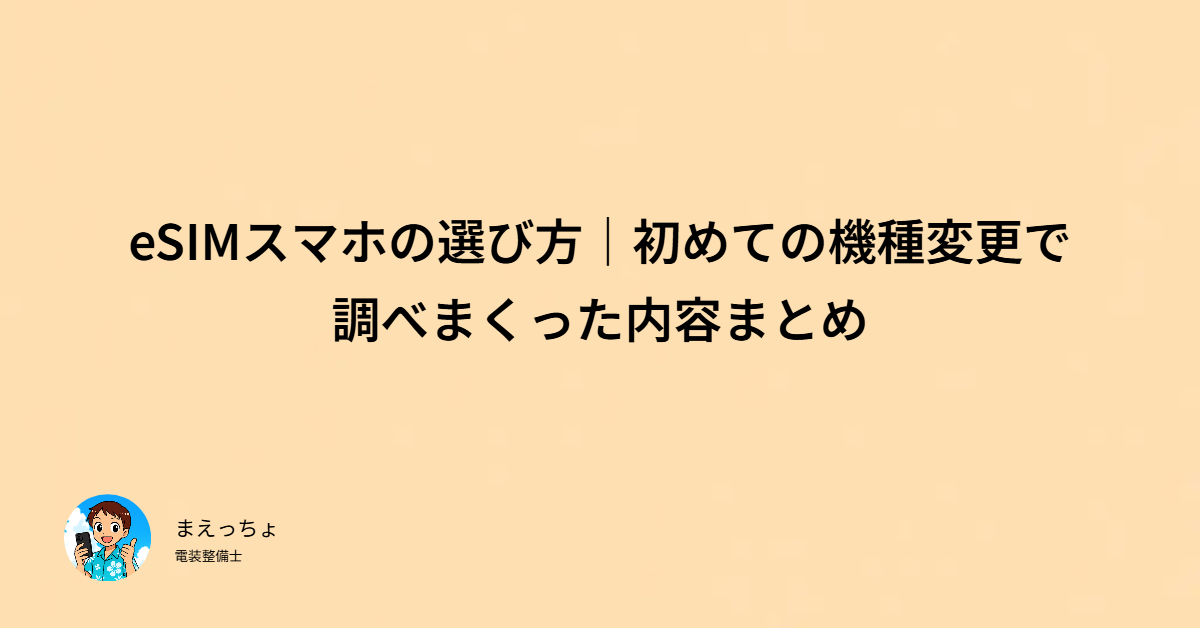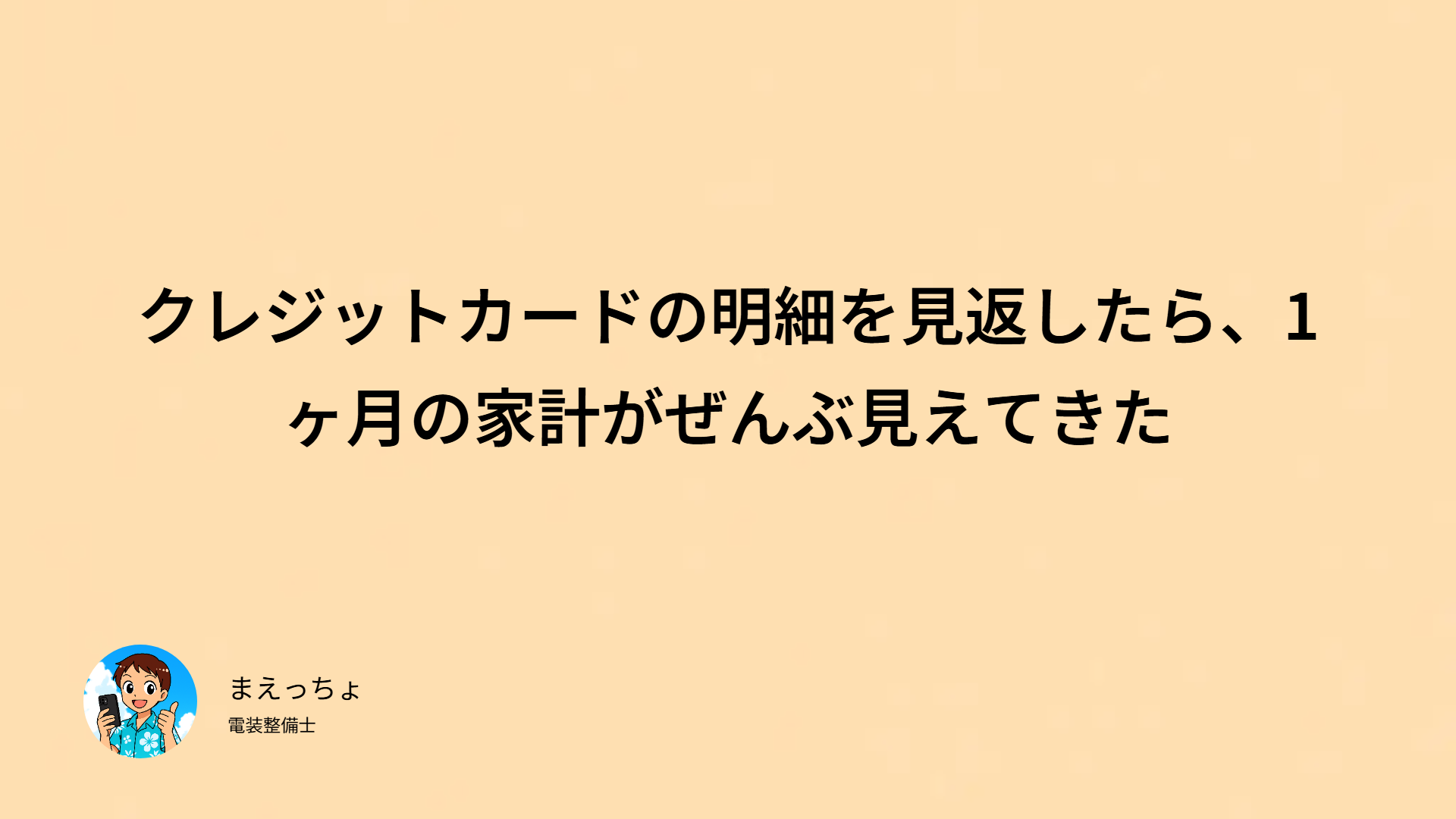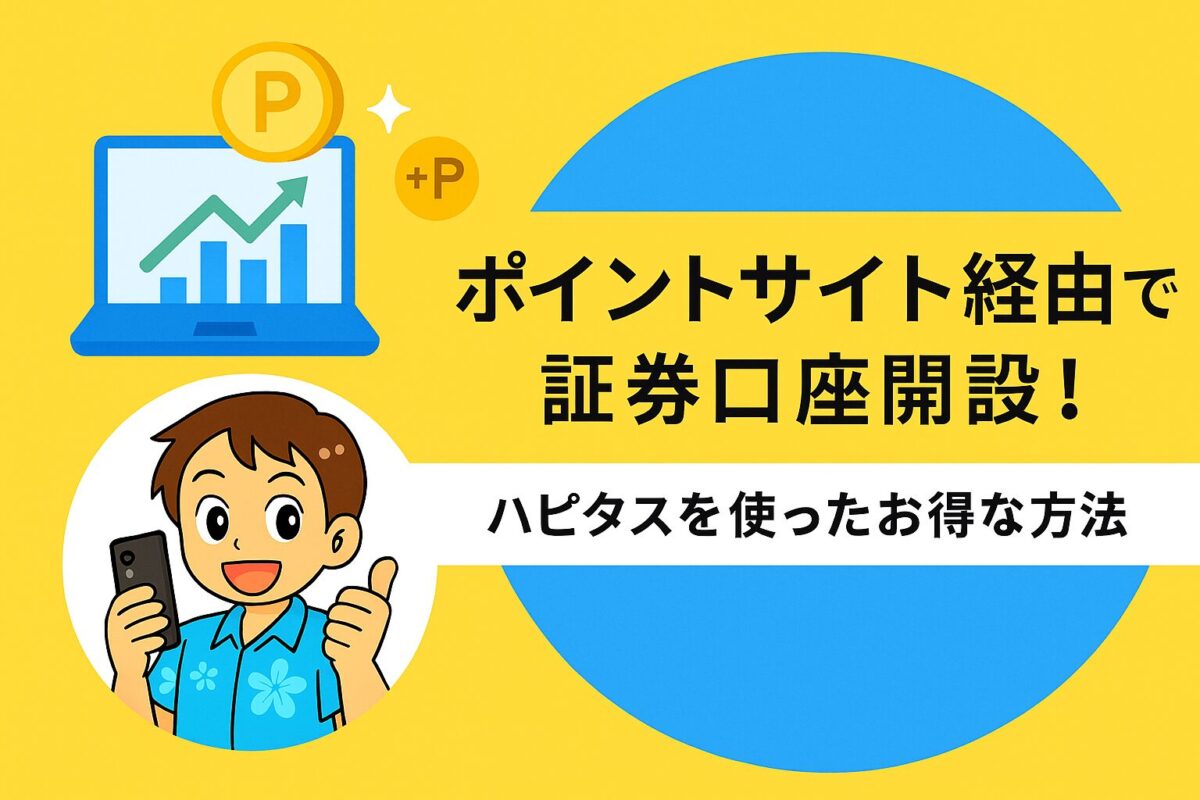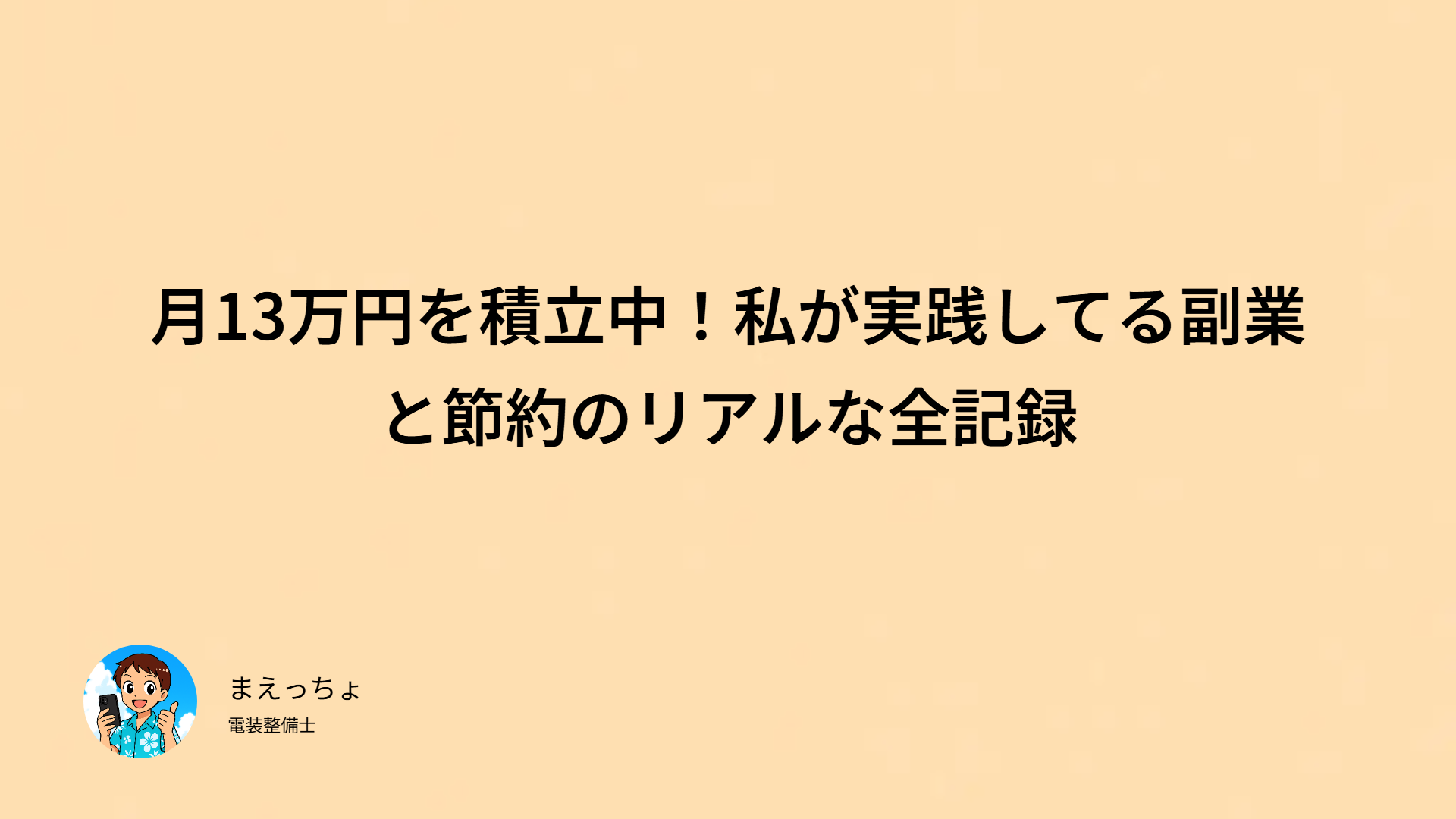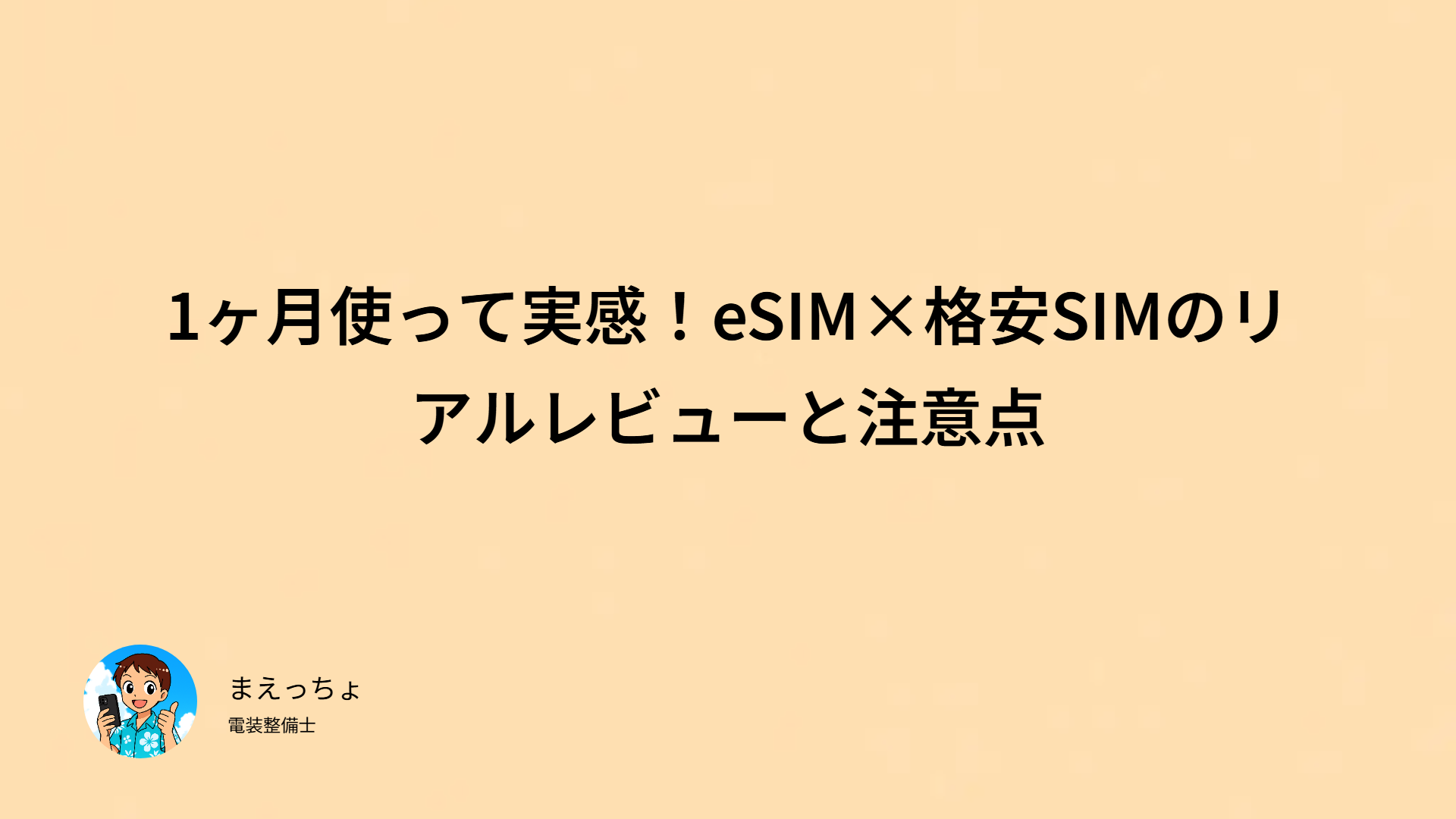家計管理を通じて黒字化した方法|ズボラな私でも続けられた5つの工夫
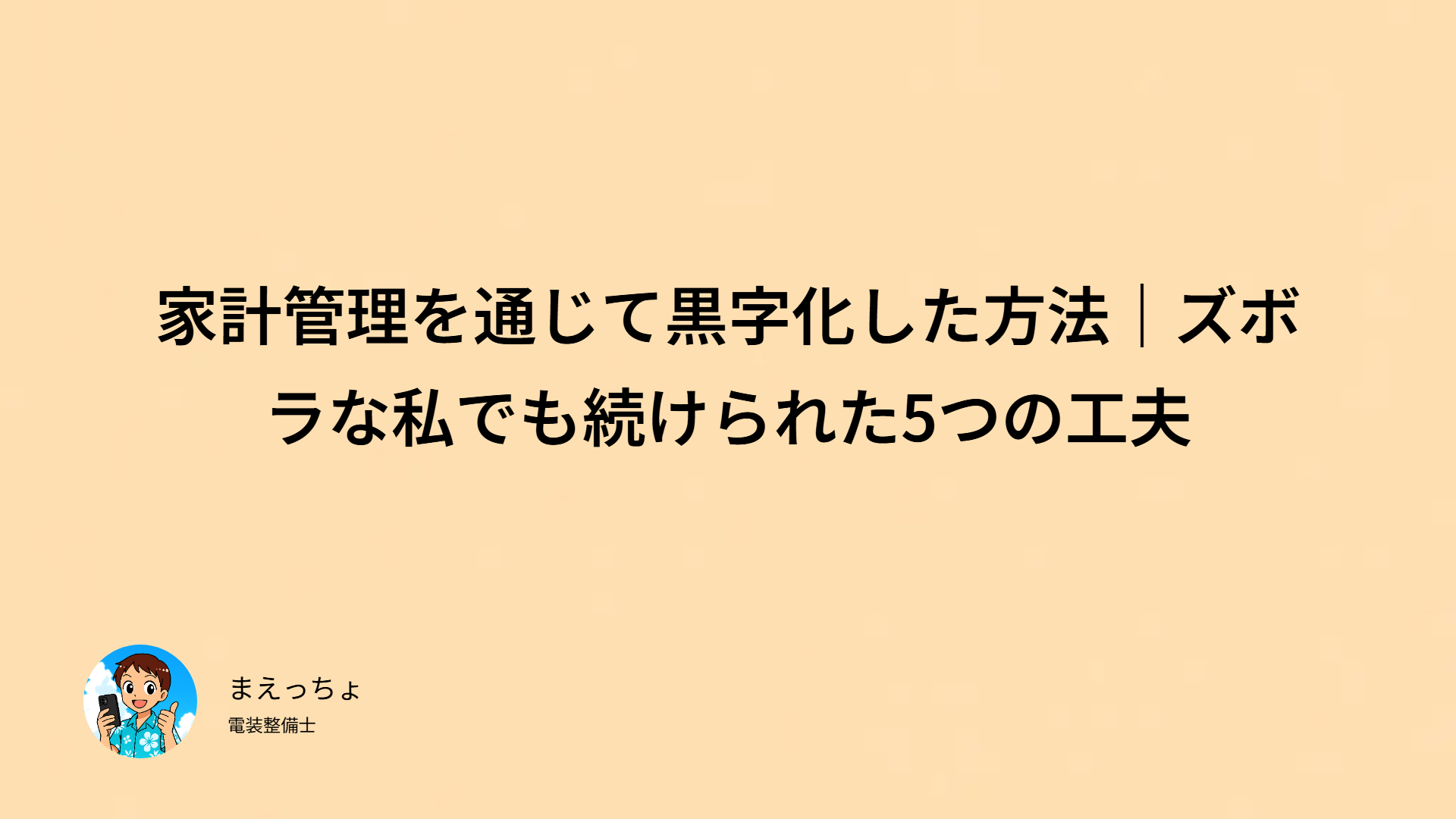
毎月、なんとなくお金が減っていく。
そんな不安を感じながらも、家計を見直すきっかけがつかめない。
実は、以前の私もそうでした。
家計には無頓着で、貯金は妻にまかせっきり。
でもあるとき気づいたんです。
赤字になると、積立投資が止まってしまう。
最悪、貯金を崩すしかない。
家計のことを知らないのは、とても怖いことだと思いました。
この記事では、そんな私が実際に実践してきた
家計管理を通じて黒字化する方法を、家計管理初心者にもわかりやすく紹介します。
家計管理をざっくりでも始めたら、見えてきた安心感
最初は家計に興味がなく、妻にまかせていた
私が家計管理に向き合いはじめたのは、結婚して何年も経ってからのことでした。
それまでは、家計なんて正直どうでもいいと思っていて、すべて妻に任せていました。
支出の詳細も、貯金の残高も、ほとんど把握していませんでした。
けれど子どもが生まれ、将来のことを本気で考えたとき、「このままではまずい」と思うようになりました。
お金の流れを把握していない状態では、何に使っているのかもわからず、貯金も増えません。
家計のことを“他人ごと”のままにしておくのは、家族を守る立場として不安すぎる。
そんな危機感が、私を変えてくれました。
「なんとなく黒字」では安心できないと気づいた
それまでは「赤字にはなっていないから大丈夫」と思い込んでいました。
でも、黒字かどうかも、毎月いくら余っているのかも、実際のところは“なんとなく”の感覚だけ。
けれど現実には、想定外の出費が重なることもあります。
たとえば医療費、家電の買い替え、車の修理。
そんなときに家計が赤字だと、貯金を崩さなければいけない。
この事実に気づいてからは、「万が一、病気や転職で収入が止まったら…」と想像したとき、背筋がゾッとした。
そんな現実にようやく気づいたのです。
きちんと支出を把握し、毎月しっかり黒字をキープできる家計にしたい。
その思いが、私の家計管理の原動力になっています。
夫婦で支出を共有するようになって変わったこと
これまでの私は「お金のことは妻の役目」と思い込んでいました。
でも今は、夫婦で支出を共有しながら、お互いにざっくり家計を見守っています。
最初は「そんな細かいこと言わないで」と言われたことも。でも今では、月1回だけ振り返るのが我が家のルールになった。
月ごとにざっくりと家計を振り返るだけでも、ムダ遣いの抑止になります。
これは私たち夫婦にとって、大きな意識の変化でした。
家計のすべてを細かく記録するわけではなく、あくまで“共有と把握”が目的。
この「ゆるいつながり」が、お金に対する意識を少しずつ変えてくれました。
ネット銀行&キャッシュレス管理のラクさと課題
我が家では、7割以上の支出をキャッシュレスで管理しています。
使った金額はアプリで自動反映されるため、家計の流れがすぐに見えるのは大きなメリットです。
また、銀行もネット銀行を利用しているので、スマホひとつですぐ残高を確認できます。
「今、いくら使って、いくら残っているのか」がリアルタイムで把握できるのは、かなり便利です。
ただし、現在メインで使っている銀行が3つあるため、管理が少し面倒なことも事実。
口座が多すぎると、どこにいくらあるかが一目でわかりづらくなります。
今は1つ、最低でも2つに整理しようかと検討しているところです。
「面倒だから」と避けていた仕組みも、いざ始めてみたら驚くほどラクでした。
家計管理は、完璧じゃなくていい。“ちょっと始めるだけ”で、安心感が手に入ります。
ズボラな私でも続けられた5つの工夫
①支出の見える化からスタートした
家計を整えるには、まずお金の流れを把握することがスタートラインでした。
私自身、家計管理を始めたばかりのころは、支出の明細なんて見たこともなく、
カードの引き落とし額も「たぶん大丈夫でしょ」と根拠のない感覚でやり過ごしていました。
最初に取り組んだのは、支出の見える化です。
とはいえ、いきなり完璧な家計簿をつけるようなハードルの高いことではありません。
月末に「何にどれだけ使ったか」をざっくり振り返る程度の、ゆるいやり方から始めました。
“なんとなく”から“ざっくり把握”に変えただけで、「ムダ遣い」がどんどん浮き彫りになってきます。
「意外とコンビニで使ってるな」「サブスク多すぎかも」など、自分でも驚く発見がありました。
この時点で、家計管理を通じて黒字化する方法の第一歩を実感できたのです。
②固定費の見直しが黒字化のカギだった
支出全体をざっくり把握できるようになると、「毎月確実に出ていくお金=固定費」の重みが見えてきました。
保険、スマホ代、サブスク、光熱費、住宅ローンなどを合わせると、我が家の出費の30%が“自動で流出していた”のです。
この状態を変えるために取り組んだのが、固定費の見直しです。
たとえば私自身、高校生の頃に入ってそのまま放置していたダーツのサブスクに気づいて、即解約。
、動画配信サイトを解約。妻は、解約したことに気づいていません(笑)
こうした「なんとなく継続」の固定費が、知らないうちに家計を圧迫していたのです。
保険も、「万が一」に備えすぎて過剰になっていた、生命保険(月8千円節約)の見直しに成功しました。
私の保険の見直し実例(遺族年金を加味した上)です:
- ①(3歳息子)20歳までの生活費確保のため
- ②17年分の生活費の計算
- ③17年分の生活費が出る死亡保険加入
- ※資産が1000万超えたら保険も解約予定
こうした見直しは一度やれば効果がずっと続く、手間ゼロで実行できる節約法だと実感しています。
もしまだ固定費を見直していないなら、それだけで年間10万円以上の差が出るかもしれません。
③格安SIMに乗り換えて、通信費を大幅に削減
中でも一番インパクトがあったのは、スマホ代の見直しです。
以前は夫婦2人で月に2万3,000円以上もかかっていましたが、格安SIMに乗り換えたことで月2,780円まで圧縮できました。
年間で20万円以上の節約。
しかも通信の品質にも特に不満はなく、むしろ「これまでの金額はなんだったのか」と驚くほどでした。
このように、「一度の見直し」で毎月の出費を根本から変えられる実感はとても大きなものでした。
家計管理を通じて黒字化する方法は、意外と“気づいていない固定”を疑うことから始まるのかもしれません。
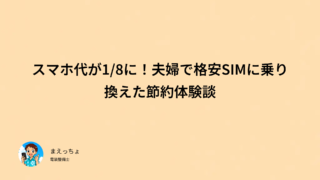
④給料が入ったら投資用口座に移す
固定費の削減に加えて、私がもう一つ取り入れたのが「先取り投資」の習慣です。
給料が振り込まれたらすぐに、証券口座へ移すようにしています。
“余ったら投資”ではなく、“先に投資して、残りで生活”という発想の転換です。
この仕組みを続けることで、家計に自然とメリハリが生まれ、
「黒字が前提」という感覚が育ちました。
ちなみに私が積み立てているのは、「eMAXIS Slim S&P500」という米国株インデックスS&P500連動型(ヘッジなし)です。
長期分散投資に向いており、手数料も低いため、共働き家庭にも向いていると感じています。
このルールのおかげで、支出全体への意識も高まり、結果的に家計管理を通じて黒字化する方法の核となる習慣になっています。
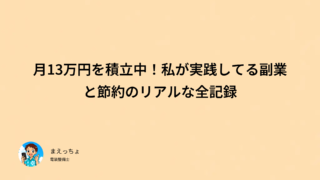
⑤浮いたお金が副業や投資の種銭になった
こうして生まれた毎月数万円の余力は、我が家にとって“ただの節約”では終わりませんでした。
そのお金を原資に、私は副業としてブログを始めたり、自己投資をしたりと、
「お金を守る」から「お金を育てる」ステージへと自然に進んでいったのです。
特にブログは、今では趣味と実益を兼ねた存在になりました。
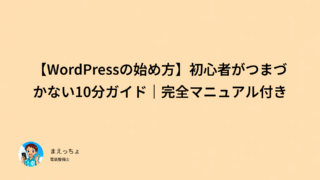
節約の先に「次の選択肢」があることで、家計改善もモチベーションが続きます。
最初は赤字をどうにかしたかっただけ。
けれど、やってみたらその先に「人生を変える行動資金」が生まれた。
それこそが、私にとっての、家計管理を通じて黒字化する方法の本質です。
家計管理を通じて得られた3つの安心
毎月黒字になることで気持ちにゆとりが生まれた
毎月、家計が黒字になるようになって、何より変わったのは精神的な開放感でした。
たとえば、給料日前の1週間が近づくと、以前は「あと何日、どうやってしのごう…」と電卓を叩いていたのに、
今は「ちょっと使いすぎたかも」くらいで済む。
そんな小さな心の変化が、日々の選択に前向きさをもたらしてくれるようになりました。
たとえ1万円でも「今月は残った」と思えるだけで、気持ちの緊張がほぐれます。
「使っても、赤字にならない」と思えるだけで、家族との会話や週末の過ごし方にも余裕が出ました。
貯金に手をつけずに済む安心感
家計改善に本気になった大きな理由のひとつが、「毎月赤字だと、貯金を崩すしかない」という現実でした。
あるとき、急に息子が体調を崩して入院することになり、1週間の医療費や交通費が想像以上にかかりました。
そのとき、「あ、今月の黒字で全部まかなえた」と気づいた瞬間、ほんとうにホッとしたんです。
貯金がなかったころは、生活防衛費“いざというときの最後の砦”、に頼っていたこともあった。
その事実が、自分の中で大きな不安材料になっていたのだと思います。
将来に向けて「資産形成」への道が開けた
毎月黒字を出せるようになって、ようやく「貯める」や「増やす」といった言葉が現実味を帯びてきました。
それまでは「NISAってなんか難しそう」「副業は自分には無理かも」と思っていたのに、
小さくても“使えるお金”が毎月生まれるようになると、自然と「ちょっとやってみようかな」と思えるようになったんです。
私が最初に手をつけたのは、積立投資とブログ運営。
どちらも最初は不安だらけでしたが、投資信託の評価額が少しずつ育っていくのを見て、
「お金って“働かせる”こともできるんだ」と感じられたのは大きな発見でした。
家計管理を通じて黒字化する方法は、ただ節約するだけではありません。
「未来に希望を持てるお金の使い方」を選べるようになることが、本当の価値だと私は思っています。
家計管理を続けるコツと私のルール
完璧を目指さず“ざっくり管理”でOK
家計管理というと「すべて記録しなきゃ」「細かく仕分けなきゃ」と考えがちですが、私の場合はかなりざっくりです。
たとえば、家計簿アプリを使わず、現金での支出は週に1回、キャッシュレスでの支出は月に1回ざっくりメモするだけ。
完璧を目指すと、それが負担になって続かなくなる。
だから私は、家計管理を通じて黒字化する方法として「ざっくりでも把握する」ことを大切にしています。
目安として、「今月いくら使ったか」が大きくズレなければOK。
それくらいの感覚でやっている方が、家計管理は長く続けられると感じています。
夫婦で月イチの支出確認をしている
家計管理を1人で抱え込むのは、なかなかしんどいものです。
だから我が家では、月に1回だけでもいいので、夫婦で支出をざっくり確認する時間をとっています。
「今月は外食が多かったね」「サブスク見直してみようか」など、
家計について話すだけで、お互いの使い方に対する理解が深まります。
1番大事なことは、夫婦間でお金の価値観をすり合わせること。
この月1確認が、家計管理を通じて黒字化する方法の中でも、我が家の習慣として根付いています。
家計簿は使わず、シンプルなメモ管理だけ
私は、昔から家計簿が続いた試しがありませんでした。
つけても1ヶ月で終わる、気づいたらズボラになって放置する。そんなことの繰り返しでした。
そこで思いきって家計簿をやめて、「ノートに使った金額をメモするだけ」に変えました。
やっていることは、現金でしか買えない食費や、日用品などのざっくりした記録のみ。
その記録とクレジットカードの利用明細を見たら月のざっくりとした支出は分かります。
それでも、「先月と比べて今月はどうか」「赤字になりそうか」はわかります。
これで十分、家計管理を通じて黒字化する方法として成り立つと実感しています。
気をつけていることとよくある落とし穴
「見直したのに赤字」の原因は変動費にあり
家計を黒字化するには、まず固定費の見直しが効果的です。
しかし、それだけで安心してしまうと、思わぬ落とし穴にハマります。それが「変動費」です。
私自身、固定費を見直したあとに油断し、「これくらいなら大丈夫」とコンビニでおやつやコーヒーを買う頻度が増えてしまいました。
小さな出費のつもりでも、積み重なると月末には「えっ、赤字!?」と焦ることに。
この経験から、変動費に意識を向けることの重要性を痛感しました。
とくに、固定費を削った安心感から気が緩むタイミングは要注意です。
「特別費」を見込んでいないと苦しくなる
毎月の予算は把握していても、意外と見落としがちなのが「特別費」です。
旅行、プレゼント、車の修理、家電の故障…それらは毎月ではないけれど、確実に発生する支出です。
私も以前、冷蔵庫が突然壊れて買い替えることになり、想定外の10万円超の出費に一時パニックに。
「これは完全に計算外だった…」と、家計管理の甘さを痛感しました。
それ以来、「年に〇万円は特別費として使う」とざっくり見積もるようにしました。
車の修理やレジャーなど、あらかじめ想定しておけば、急な出費にも落ち着いて対応できます。
こうした見通しを持つことも、家計管理を通じて黒字化する方法の一部として欠かせません。
節約ストレスが溜まらない仕組みをつくる
節約や家計管理は、続けることがいちばん大事。
そのためには「節約疲れ」や「我慢のしすぎ」でストレスを抱えない仕組みが必要です。
我が家では、月2回の「ご褒美デー」を設けています。
好きなお寿司を食べたり、ケーキを買ったりと、思いきり楽しむ日です。
この日があることで、日々の節約も前向きに取り組めます。
「節約=我慢」ではなく、「やりくりの中で楽しむ」こと。
これこそが、家計管理を通じて黒字化する方法を継続するための大事な工夫だと思っています。
家計管理が面倒な人にこそ伝えたいこと
やる意味あるの?と思ってた過去の自分へ
かつての私は、「家計管理ってやる意味あるの?」と本気で思っていました。
どうせ赤字、どうせ続かない、自分には無理。そうやって、都合のいい言い訳を並べて、見て見ぬふりをしていたんです。
でもあるとき気づきました。
見なければラク。でも、お金の不安は、いつか現実になるということに。
ほんの少しの勇気で、「ちょっとだけ見直してみよう」と思えた。
その小さな一歩が、今の自分をつくったのだと確信しています。
だから過去の自分に、今ならこう言いたい。
「難しく考えなくていい。完璧じゃなくていい。ほんの少しだけ、家計と向き合ってみて」と。
完璧じゃなくても続けることが大事
私は今でも、家計簿アプリは使っていません。
やっているのは、ノートに「食費:4,500円」「外食:2,000円」といったメモを週に1回つけるだけの、超シンプルな管理です。
それでも「今月、何にどれくらい使ったか」「黒字か赤字か」が見えるようになります。
つまり、数字の正確さよりも、“気づき”のきっかけが大事なんです。
完璧を求めると、途中でしんどくなります。
でも、たとえざっくりでも続けていれば、家計管理を通じて黒字化する方法はちゃんと身についていきます。
家計管理を通じて黒字化する方法は誰でもできる
家計管理に、特別なスキルは必要ありません。
高機能なアプリも、几帳面な性格もいらない。
本当に必要なのは、「ちょっとだけ見てみようかな」という気持ちと、ざっくりでも続ける習慣です。
私も最初はお金に無頓着で、支出も貯金額もまったく把握していませんでした。
でも支出の流れが少しずつ見えるようになると、不思議と「このお金、どう使おう?」と考えるようになるんです。
家計管理が苦手な人ほど、完璧を目指さずに、自分に合った“ゆるい続け方”を見つけてほしい。
それが、家計管理を通じて黒字化する方法のいちばんの近道だと思っています。
最初の一歩は“ざっくり把握”からで十分
「毎月いくら使っているか、なんとなくしか覚えてない」──それでOKです。
「最近コンビニ多いかも?」「あれ、サブスクって何個入ってるんだっけ?」と気づけるだけでも十分価値があります。
実際、私も「高校時代に入ったまま放置していたダーツのサブスク」や、
「副業で忙しくてみもしない動画配信サイト」に気づいたことで、ムダ遣いを減らすきっかけになりました。
最初から全部を把握しようとしなくていい。
まずは“なんとなく”を“ざっくり”に変えるだけ。
それだけで、家計管理を通じて黒字化する方法への一歩が踏み出せます。