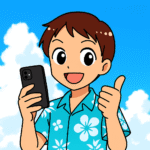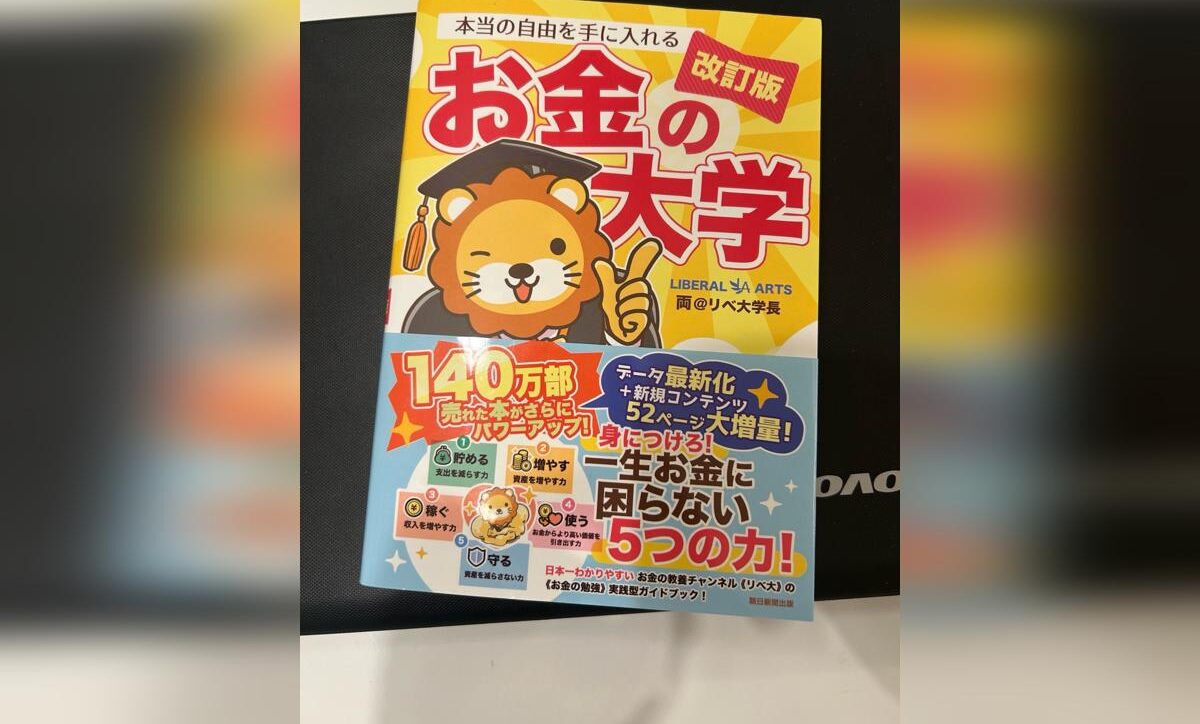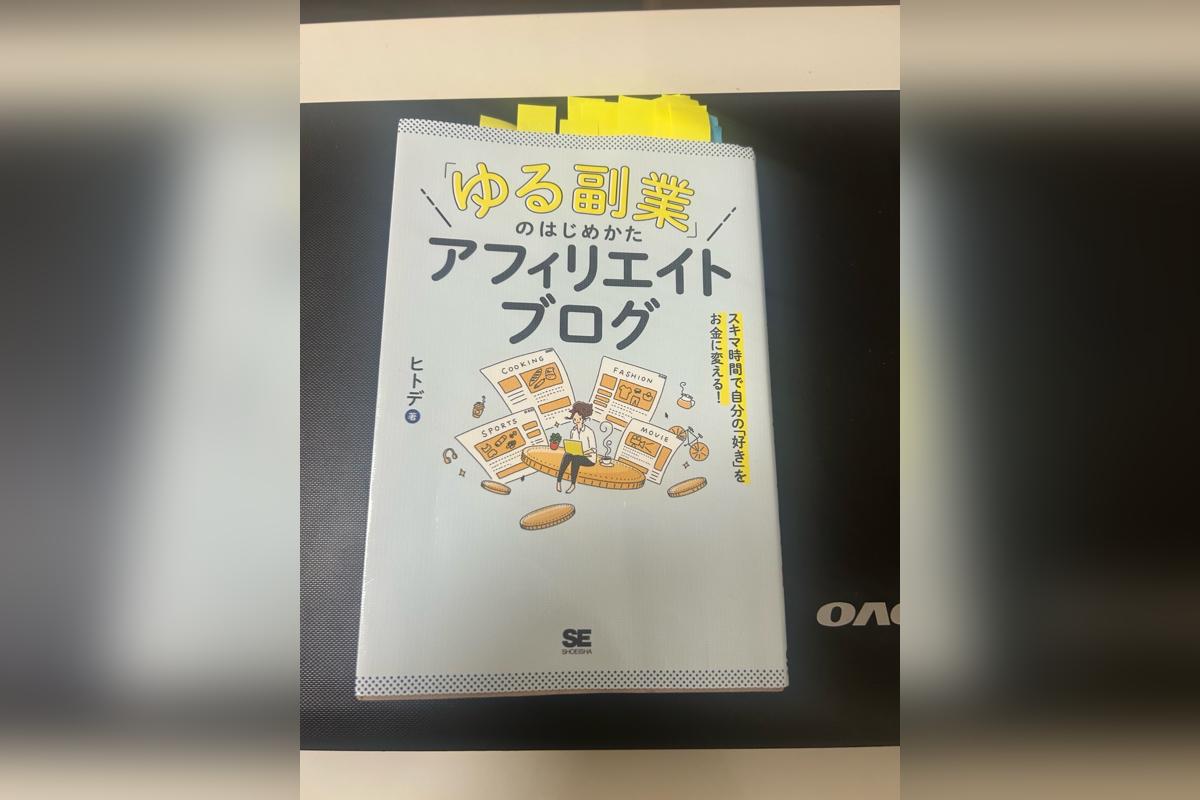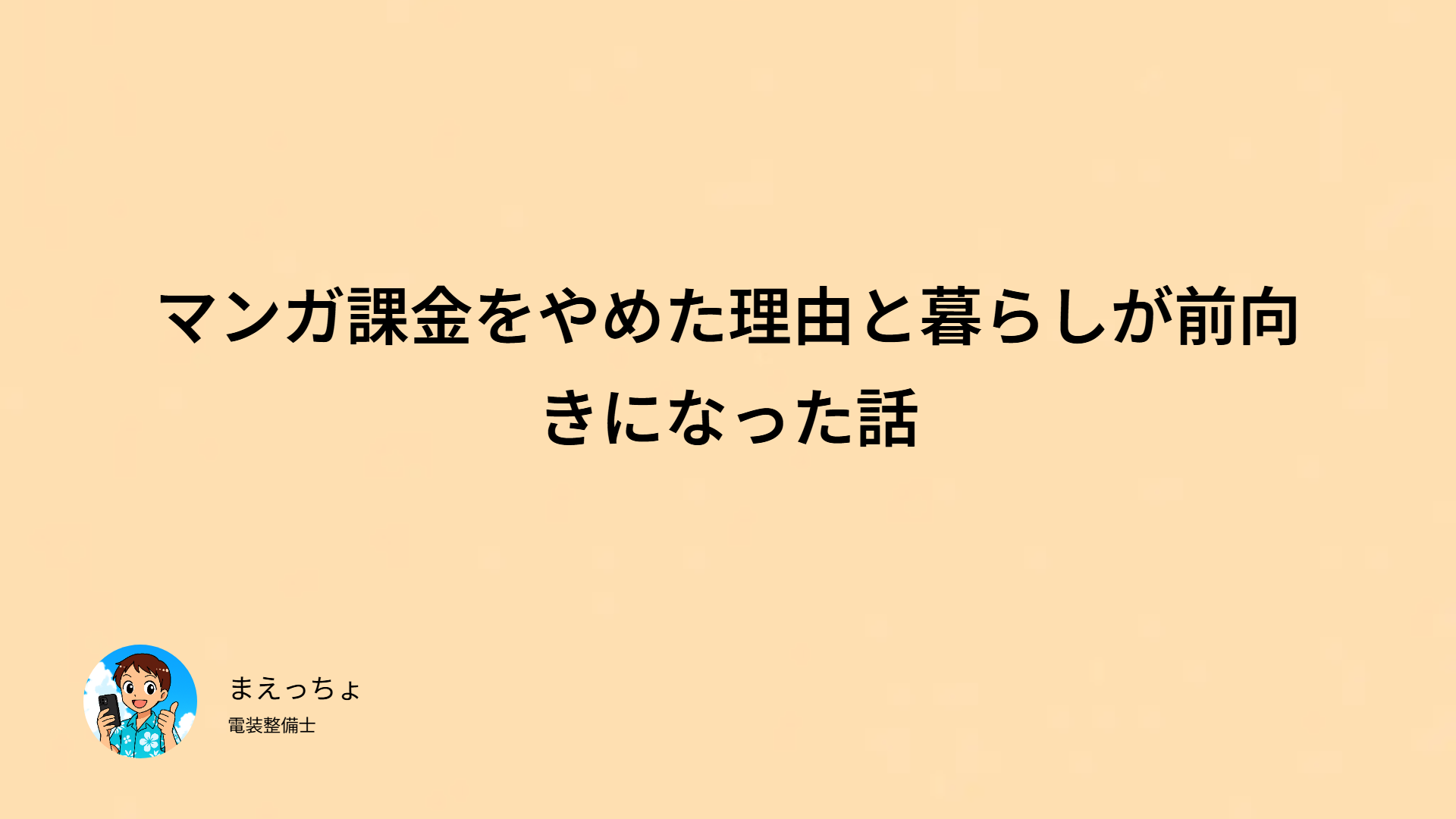【レビュー】金持ち父さん貧乏父さんで変わったお金の考え方5選
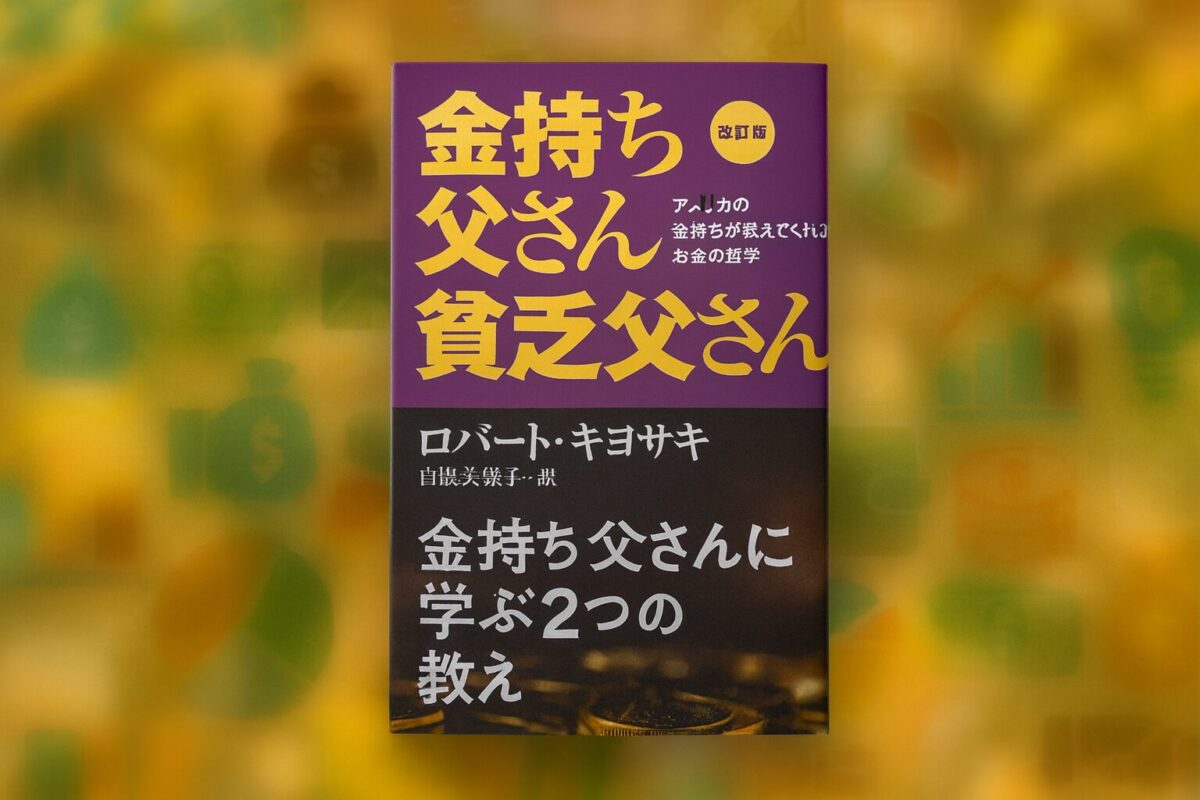
お金のことって、なぜか学校でも家庭でもちゃんと教えてもらえなかった。
だからこそ、私は「金持ち父さん貧乏父さん」を読んで衝撃を受けた。
この本は、ロバート・キヨサキ氏が語る“2人の父親”の対比を通じて、「お金の常識」を根本からくつがえしてくる。
読んでいくうちに、自分がいかに「お金に働かされていたか」に気づかされ、
今では「お金に働いてもらうには?」と自然に考えるようになった。
この本を読んで変わったお金の考え方・価値観を5つ紹介していくよ〜

お金がないじゃなく「どうやって作るか?」と考える習慣
金持ち父さんと貧乏父さんの決定的な違い
私がこの本を読んで最初に「グッ」と来たのは、金持ち父さんと貧乏父さんの“お金に対する考え方の違い”だった。
貧乏父さんは、「それを買うお金はない」とすぐに口にしていた。
一方で、金持ち父さんは「どうやったらそのお金を手に入れるか?」を考えるようにしていた。
この言葉の違いが、そのまま将来の経済力の差に直結している――そんなふうに感じた。
「お金がない」を口癖にしないための思考習慣
この違いに気づいた瞬間、
「なるほど…! だからこそ自分の頭で考えることが大事なんだ」
と、背筋が伸びるような気持ちになった。
何かをあきらめる前に、まず「どうしたら達成できるかを考える」クセをつける。
これは日常生活にも副業にも家計管理にも応用できる、まさに“金持ち父さん的な思考”の入り口だと思う。
ビジネスの世界を4つに分けると
キャッシュフロー・クワドラントとは?
本書では、ビジネスの世界は4つのタイプに分けられるという考え方が紹介されている。
それが「キャッシュフロー・クワドラント」と呼ばれるフレームワークだ。
(※より詳しくは続編『金持ち父さんのキャッシュフロー・クワドラント』で解説されている)
- E:Employee(従業員)
- S:Self-employed(自営業者)
- B:Business owner(ビジネスオーナー)
- I:Investor(投資家)
ほとんどの人はE(従業員)として働き、人生を終える。
時間と労働力を差し出して収入を得る“時間労働型”だ。
一方で金持ち父さんは、「お金に働かせる」B(ビジネス)やI(投資)こそが自由への道だと教える。
初めて知った“自分のポジション”
この考え方に出会って、私は思った。
「あ、自分って完全にE(従業員)だな…」と。
けれど、ブログという副業を始めたことで、少しずつS(自営業者)的な要素も持つようになってきた。
さらに、NISAを使って投資信託を積み立てている自分は、少しだけI(投資家)の側にも足を踏み入れていると気づいた。
稼ぎ方の選択肢が広がったという気づき
「働く=就職するしかない」と思い込んでいた自分にとって、
このクワドラントは新しい地図だった。
いまの自分はE+S+Iの複合状態。
まだB(ビジネスオーナー)ではないけれど、「その先に道がある」と思えるだけで、人生の見え方が変わってきた。
資産と負債の定義が180度ひっくり返された瞬間
「資産=プラス、負債=マイナス」じゃなかった
本書では、一般的にイメージされる“資産”と“負債”の定義を、まったく違う切り口で教えてくれる。
資産とは、私のポケットにお金を入れてくれる
負債とは、私のポケットからお金をとっていく
たとえば、「マイホームは資産」と思っている人も多いが、金持ち父さんの視点では「負債」となる。
なぜなら、住んでいる限りお金を生まないからだ。
このシンプルだけど強烈な定義に、私はかなりショックを受けた。
住宅ローンを組んで持ち家を買った自分にとって、「資産のつもりだった家が、実は負債だ!」と言われたからだ。
マイホーム=負債という現実にハッとした
特に印象に残ったのは、93ページで紹介されていた「持ち家に関する5つの主張」。
すべてが合理的で、でも自分のこれまでの考え方を根底からひっくり返されるような内容だった。
正直、「もっと早くこの本に出会っていれば…」と悔しい気持ちにもなった。
マネーリテラシーがないまま、家を持つ“順番”を間違えてしまったのかもしれないと考えさせられた。
でも、そう思えたこと自体が、この本の価値だったとも感じている。
自分の「資産」は本当に資産なのか?
読みながら「じゃあ今の自分はどんな資産を持ってるんだろう?」と考えてみた。
…正直、株式くらいしかなかった。
本書では「不動産、株、債券、ビジネス」など、7つの本当の資産が紹介されている。
その中で、自分が持っているのは1つだけ。
「もっと資産の幅を広げなきゃ」と思わされたし、それ以前に“お金の使い方そのもの”を見直したくなった。
自分は中流以下だと気づかされた
財務諸表がリアルすぎた
「金持ち父さん貧乏父さん」では、お金の流れを理解させるために“財務諸表”の図が何度も登場する。
それを見たとき、私は自分のことがそのまま描かれているように感じた。
会社員として給料をもらい、生活費に消え、たまに娯楽に使い、資産はほぼ増えていない。
典型的な“中流以下”の構造に、私自身がモロに当てはまっていた。
これは正直ショックだった。
だけど、今このタイミングで気づけたことは大きな意味があると感じた。
ひとつだけ“誇れたこと”があった
そんな中で、ひとつだけ嬉しかったことがある。
それは、収入が入ったらまず資産にお金を回すという自分の習慣が、
本書で金持ち父さんが勧めていた考え方と一致していたこと。
私の場合、生活費よりも先に「NISA口座に投資する」という流れがすでに定着していた。
これはなんとなくやっていたことだったが、「自分の選択は間違っていなかった」と確信を持てた。

お金の使い方を“資産視点”で見るようになった
「金持ち父さん貧乏父さん」を読んでから、身の回りのことに対して「これは資産か?負債か?」と考えるようになった。
家計簿アプリで支出をチェックするたび、
「これはただ消えていくお金じゃないか?」と問い直すようになった。
お金の流れが変われば、人生の流れも変わる。
本書は、それを“感覚じゃなく論理で”教えてくれた一冊だった。
衝撃を受けた考え方
忙しい人が一番の怠け者
本書の中で、もっとも強烈に刺さった一言がこれだった。
忙しい、時間がない、余裕がない――
そうやって自分を正当化して動かない人ほど、本当は“変わること”を避けているのかもしれない。
この言葉に触れたとき、私はドキッとした。
自分も「忙しい」を理由に、何かを後回しにした経験が何度もある。
けれど本書は、その状態こそが「思考停止」であり、「怠け者の状態」だと突きつけてくる。
耳が痛い。けれど、だからこそ印象に残った。
一番欲しいものを、まず与えるという逆転の発想
金持ち父さんが伝えていたもうひとつの考え方――
それは「お金が欲しいなら、まず誰かにお金を与える」だった。
正直、何を言ってるのか分からなかった。
でも読み進めていくうちに、
「自分が不足していると思っているものを、まず他人に与えることで、やがて自分に返ってくる」
という循環の考え方に心を動かされた。
私はまだこの考え方を実践したことがない。
でも「今できる範囲で試してみよう」と思った。
まとめ|「金持ち父さん貧乏父さん」を読んで
『金持ち父さん 貧乏父さん』は、お金について考える“きっかけ”をくれる一冊だった。
本を閉じたとき、思ったのは「もっと早く出会いたかった」ということ。
だからこそ、この記事をここまで読んでくれたあなたには、ぜひ手に取ってほしい。
続きは本書の中に――あなたの考え方を変える一行が、きっと待っています。
- 本当の「資産」とはなにか、お金を生み出していくその考え方
- ビジネスの世界はE(従業員)・S(自営業)・B(ビジネスオーナー)・I(投資家)の4つに分かれるという視点
- 忙しい人こそ怠け者であり、欲しいならまず与えるという逆転の思考法